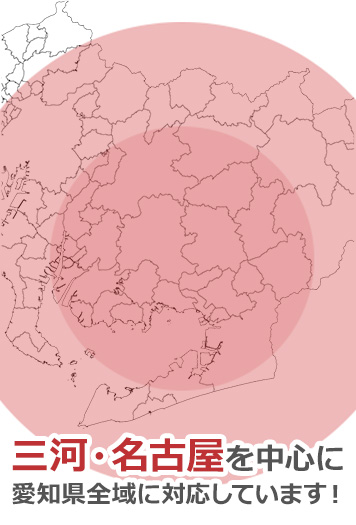2024年6月から所得税と住民税の定額減税額を控除する給与等の源泉徴収事務がはじまります。
給与担当者はその対象者を把握し、どのような対応をするべきか解説します。
定額減税の概要
定額減税は、所得税や法人税などの税金を一定の金額だけ削減する制度です。
これ制度は、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、
デフレ脱却のための一時的な措置として、減税を行い、物価高対策として実施するといった背景があります。
定額減税の対象者と対象額
対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)です。
対象額
納税者およびその扶養家族1人に対する減税額は1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。
3人家族の場合、年間で総額12万円に達します。
条件に当てはまらず、定額減税の対象外になってしまう場合は、給付金の支給が行われます。
住民税非課税世帯には7万円、所得税が非課税で住民税が課税の低所得世帯には10万円が支給されます。
企業が対応すべき実務とは
定額減税は2024年6月支給給与から対象となります。
そして、企業が定額減税に対応するためには、以下のような実務が考えられます。
所得税
①給与受取者の見込みで2024年年収2000万を超えないか確認
②給与受取者に令和6年扶養控除申告書に変更事項がないか確認 ※配偶者所得48万円を超えていないかも確認
③扶養控除申告書及び定額減税のための申告書を見て、扶養人数確認後管理シートへ記入 ※給与計算ソフトを使用している場合は、管理シートをソフト内で作成できるため、Excelでの作成は不要になります。
④給与計算時に源泉所得税を控除
⑤管理シートへ控除した金額の記入
⑥残額があった場合は、夏賞与及び給与7月支給時に減額。
これらの実務を適切に実施することで、企業は定額減税に対応し、税務リスクを最小限に抑えることができます。
住民税は、2024年6月分は徴収せず、 定額減税後の税額を翌月の2024年7月分~2025年5月分の11か月に均一にして徴収されます。
定額減税における注意点
〇所得税定額減税の生計配偶者と扶養家族の範囲
所得税定額減税は、所得税法上の範囲と違うため注意が必要となります。
・同一生計配偶者の範囲
①居住者
②納税義務者(本人)と生計を一にし、かつ、2024年度の合計所得額が48万円以下
(給与所得のみの場合は年収103万円以下)
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けておらず、白色申告者の事業専従者ではない
・扶養親族の範囲
①居住者
②納税義務者(本人)と生計を一にし、かつ、2024年度の合計所得額が48万円以下 (給与所得のみの場合は年収103万円以下)
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けておらず、白色申告者の事業専従者ではない
④配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族) または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
〇扶養控除申告書の内容に変更 提出済みの扶養控除申告書の内容に変更があった場合は、 【年末調整に係る定額減税のための申告書】に記載が必要となります。
〇年末調整時に精算する 基本的には、2024年6月支給給与から定額減税の対応をしなければいけません。 しかし、6月時点で下記に当てはまる方は年末調整時に精算となりますので注意が必要です。
・令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職など、 「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合
・令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合
まとめ
事務作業が増えるため、Excelや手書きで給与明細を作成している方は、 これを機に給与計算ソフトを導入してみるのはいかがでしょうか?
弊社では導入支援及び給与計算代行もやっておりますので、もしお悩みでしたらご連絡ください。